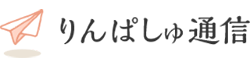第2回 診断がつく前に「3つの備え」をしておこう〜より良い治療につなげるためにできることとは?〜

医療法人財団順和会 赤坂山王メディカルセンター
(国際医療福祉大学医学部 血液内科学 教授)
畠 清彦(はたけ きよひこ)先生
リンパ腫では、診断がつく前にしておくと、その後の治療をスムーズに、そしてより良くすることができる「3つの備え」があります。それは、「継続する」「治療する」「習慣づける」の3つ。具体的にはどうすればよいのでしょうか。今回は患者さん自身が治療に取り組む前に知っておきたい「診断までにするべきこと」について、畠先生にお話をうかがいました。
1 継続する
 リンパ腫の診断までに「継続する」とは、どういうことでしょうか?
リンパ腫の診断までに「継続する」とは、どういうことでしょうか?
畠先生(以下、敬称略)リンパ腫の疑いが出ても「仕事を継続する」ということです。当院では、仕事をしながら外来(通院)で治療を行うことを推進していて、患者さんには「治療しながら今までどおりに、あるいは治療が終わったら戻るつもりで仕事をしてください」とお伝えしています。それでも、患者さんのなかには、今までどおりに働けないだろうからと、ご自身で遠慮してやめてしまう方がいらっしゃいます。確かに一定の期間は仕事をセーブする必要がありますが、近年は、リンパ腫の治療を終えてから以前と同じように仕事に戻られる方が多くなっています。治療が長期におよんだ場合に、治療費などのお金の問題もありますから、患者さんご自身が続けたいかどうかにもよりますが、できるだけ仕事を継続しながら治療に取り組むといいのではないでしょうか。

2 治療する
 リンパ腫の診断までに、何を「治療する」のでしょうか?
リンパ腫の診断までに、何を「治療する」のでしょうか?
畠 むし歯など、リンパ腫の治療中に感染症の原因となるものを治療してください。なぜなら、感染症はリンパ腫治療をさまたげるとても大きな問題だからです。リンパ腫の治療では、副作用で一時的に感染症が起きやすくなったり、感染すると重症化しやすくなることがあります。
そのため、口やお尻など、体の外から細菌やウイルスの侵入を受けやすい場所に気をつける必要があるのです。抗がん剤治療で感染症が重症化するケースは、とくに治療のはじめ頃に多いため、リンパ腫の治療を開始する前に、感染症のリスクを減らしておくことが大切です。 また、リンパ腫で使われる薬のなかには、歯が健康でないと顎の骨に副作用が出やすいものもあります。そのため、むし歯がある場合は歯科で治療をしてもらうことをお勧めしています。
また、便秘症の場合は痔※になる可能性があるので、あらかじめ便通を整えるなど治療や体調管理をしておくことが望まれます。
※痔は細菌やウイルスが体内に侵入する経路になります。

3 習慣づける
 リンパ腫の診断までに、何を「習慣づける」のでしょうか?
リンパ腫の診断までに、何を「習慣づける」のでしょうか?
畠 大きくわけて3つの習慣をつけるようにします。1つめは、「感染症を予防する」習慣です。
先ほどもお話ししたとおり、口やお尻からの感染症はリンパ腫の治療をさまたげる大きな問題になりえます。ですから、むし歯や痔などの感染症の原因となる病気をかかえている方は治療し、それらを予防する必要があります。具体的には、正しい歯みがき・うがいの習慣をつけて口のなかを清潔にし、トイレもできれば温水洗浄便座にするなど、適切な排せつ環境を整えておくようにします。
2つめは、患者さんご自身で「体調をチェックする」習慣です。とくに発熱は、治療にともなう副作用や合併症の目安となりますので、寝るまえに体温を測る習慣をつけておくといいでしょう。
さいごに、「悩みを抱えない」習慣をつけることがとても大切です。

 「悩みを抱えない」習慣とは、どういうことでしょうか?
「悩みを抱えない」習慣とは、どういうことでしょうか?
畠 日ごろから相談できる人や仲間をつくるということです。治療中にはご自身だけでは気づかないことや、対処できないことが起こる場合があります。例えば、ひとり暮らしの患者さんが体調が悪くてもがまんしてしまい、自宅で倒れているところを発見されたケースもあります。
患者さんのなかには、がまん強く、また悩みを打ちあけることに抵抗を感じて、ご自身だけでリンパ腫の治療をのりきろうとする方がいらっしゃいますが、このような事態を避けるためにも、連絡や相談ができる人を見つけておいたほうがよいと思います。医療者はもちろん、医療者以外の身近な人にも、また、身近な人がいない場合は患者会に参加するなど、悩みや困りごとをいつでも相談する習慣をつけるといいですね。

畠 診断がつくまでの間は不安な気持ちで、何も手につかないかもしれません。しかし、治療までのこういった備えが、ご自身の今後の治療に役立ちます。医師をはじめとした医療者と密にコミュニケーションをとり、一緒に治療に取り組んでいきましょう。