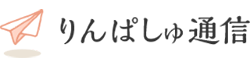食べ物がしみる-口内炎-

JCHO九州病院
副院長
小川 亮介(おがわ りょうすけ)先生
口内炎は、がんの治療中に起きる代表的な口の中のトラブルのひとつです。時間が経てば徐々に改善しますが、症状が重い場合はがんの治療だけではなく、飲食や会話などの日常生活にも影響がでます。口内炎に対しては口の中のセルフケアが重要です。口の中は自分でも簡単に観察することができるので、予防を心がけ、悪化しないように工夫しましょう。
こんな症状があらわれます

食べたり飲んだりするとしみる

食べ物や飲み物が飲み込みにくい

口の中が赤くなる、腫れる

口の中に出血しているところがある

口の中が痛い

口の中が全体的にひりひりする、焼けたような感じがする

口が動かしにくい、会話しにくい
軽い場合は口の中に違和感がある程度ですが、重くなると痛みが強くて食べ物を飲み込めなくなることもあります。抗がん剤の場合は治療後数日から10日頃になりやすく、2、3週間で徐々に改善します。また、口に近い部分で放射線療法を行った場合は治療開始後1、2週間で症状が出るようになり、治療終了後は3、4週間で少しずつ回復するといわれています(ただし、リンパ腫の種類や治療内容によって異なります)。口は、飲食や会話などの日常の動作を支える重要な器官なので、口内炎になると毎日の生活に支障が出てしまいます。治療を続けるためにも、このような症状を自覚した場合は、遠慮せずに医師や看護師に相談しましょう。

三嶋秀行 監:そのまま使える がん化学療法 患者説明ガイド, メディカ出版, p117, 2015
祖父江由紀子ほか 編:がん放射線療法ケアガイド 第3版, 中山書店, p114-115, 2019
口内炎の原因
抗がん剤は血液によって全身に運ばれるため、口の中の粘膜や歯茎にも影響を及ぼします。また、放射線治療でもダメージを受けることがあります。粘膜や歯茎の表面に傷ができると、そこから口腔内の常在細菌や真菌が侵入し、腫れたり、痛みが出たりするのです。
口内炎のケアのポイント
ここでは、口内炎の予防、症状の軽減のために、日常生活でできることや注意するポイントについてご紹介します。
 ポイント① 口の中をチェックする
ポイント① 口の中をチェックする
抗がん剤の治療が始まったら、鏡を使って毎日口の中をチェックしましょう。口内炎ができやすい唇の裏側、ほおの内側、舌の側面などを、重点的に見てください。口内炎ができていたら、大きさ、色、痛みの状態などを医師や看護師に伝えるようにしましょう。


口内炎は、最初は口の中の一部が腫れたり、飲み込むときに軽い痛みがある程度ですが、時間が経つと口の中が全体的にひりひりする、飲み込みにくい、会話しくにい、などの症状がでます。症状に応じてお薬も含め、いろいろな対処法があるので、口内炎の症状を自覚したら、早めに医師や看護師にご相談ください。
 ポイント② 清潔に保つ
ポイント② 清潔に保つ
うがいや歯みがきで口腔内を衛生的に保つことで、口内炎を予防したり、症状が重くなるのを防ぐことができます。
・うがいをする
うがいはとても手軽に行える口腔内の洗浄手段です。口内炎の予防や、痛みなどの症状を軽減させるためにも、できるだけ行うようにしましょう。

うがいの回数は、2、3時間に一度が目安です。基本的に水道水で問題ありませんが、刺激がある場合は生理食塩水を使用するのもいいでしょう。市販されている洗口液のなかには殺菌効果が得られるものもありますが、アルコールを含まず、刺激性の低いものを選びましょう。レモン水やレモン風味の炭酸水は唾液の分泌を促すため、特に食前におすすめです。

のどを洗うようなうがいではなく、口の中だけを洗浄するようなうがいにしましょう。
・歯みがき
歯みがきは、口内炎になった後でも口腔内の粘膜を傷つけないように注意しながら行うようにしましょう。

ブラシ部分が小さく、やわらかめの歯ブラシをおすすめします。ただし、かたい歯ブラシよりも歯垢(しこう)をとる効果が弱いので、時間をかけて丁寧にみがくことを意識しましょう。 歯みがきは、力を入れず、歯と歯肉(しにく)の境目に45°の角度で毛先を当てます。そして、歯ブラシの毛先が歯と歯肉の境目から離れないようにしながら、小刻みに前後に動かします。

歯や歯肉の状態に合わせて、フロスや歯間(しかん)ブラシ、スポンジブラシなどを利用してみるのもよいでしょう。舌には専用の舌ブラシが便利です。

全国歯科衛生士教育協議会 監:最新歯科衛生士教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論, 第2版, 医歯薬出版,p268-292,2020

歯みがき剤は刺激の少ないものを選び、しみる場合は水だけでみがいてもよいでしょう。
・入れ歯(義歯)の洗浄
口内炎になるまでは入れ歯を使い、口内炎に なった後は使用を控えるようにしましょう。 入れ歯はこまめに洗浄し、常に清潔にしてお きましょう。 保管容器の洗浄も忘れずに行いましょう。入 れ歯の裏側(接着面)や金属部分は汚れがた まりやすいので、専用のブラシ(義歯ブラ シ)などを使ってこすり洗いをします。洗浄 剤を使った場合は、きちんと水で洗い流し、 十分に乾燥させます。

岡元るみ子, 佐々木常雄 編:改訂版 がん化学療法副作用対策ハンドブック, 第3版,羊土社,p106,2019
日本がんサポーティブケア学会 粘膜炎部会 編:口腔ケアガイダンス第1版日本語版, p3, 2018
全国歯科衛生士教育協議会 監:最新歯科衛生士教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論, 第2版, 医歯薬出版,p268-292,2020
 ポイント③ 保湿をする
ポイント③ 保湿をする
保湿をすることで不足している唾液の働きを補い、症状を和らげることができます。
・保湿剤を使用する
口腔ケア用の保湿剤は、スプレータイプ、ジェルタイプ、洗口タイプなどがあり、乾燥の程度や使用する場面に応じて使い分けることができます。
一般の薬局でも市販されていますが、あまり刺激の強いものは避けるようにしましょう。

<保湿剤の特徴と形状>
スプレータイプ |
直接吹きかけることができるため、衛生的で簡便です。 |
ジェルタイプ |
口腔粘膜をおおうような効果があり、長い保湿維持が期待できます。 |
| 洗口タイプ | 保湿と同時に口腔内を洗浄する効果が得られます。 |
 ポイント④ 定期的な歯科検診
ポイント④ 定期的な歯科検診
口腔内には多くの細菌がいます。リンパ腫の治療によって免疫力の低下が起こると、細菌を原因とする合併症があらわれることがあります。そのため、リンパ腫治療の開始前に歯科を受診し、むし歯などに対する処置を受けておきましょう。また、リンパ腫の治療中も定期的に歯科検診を受けるなどして、口腔内の衛生環境を良好に保つようにしましょう。
 ポイント⑤ 食べ方・食べ物を工夫する
ポイント⑤ 食べ方・食べ物を工夫する
痛みなどの症状が重い場合には刺激の少ない物を用意し、咀嚼ができない場合には食べやすい形で用意するなど、食べ方を工夫してみましょう。
刺激の強い料理は避ける |
なるべく控えるもの
|
調理法を工夫する |
|
| 感染をさける |
|
| 食べ方を工夫する |
|
なお、痛みがある場合、うがいで症状が軽くなることもありますが、うがいだけで痛みがとれるわけではありません。痛みの程度によって、うがいの他に痛み止めを使う場合などいろいろな対応があるので、詳しくは医師や看護師にご相談ください。
三嶋秀行 監:そのまま使える がん化学療法 患者説明ガイド, メディカ出版, p118, 2015
代表的な感染症 口腔カンジダ症
口腔内に潜むカンジダという真菌(カビ)の一種が、免疫力の低下や唾液の減少などによって過剰に増殖することで発症する病気です。口腔内がピリピリする、ザラザラするといった違和感が症状としてあらわれますが、抗真菌薬の服用と口腔ケアで治療することができます。このような症状がみられた場合は、早めに医師、看護師、または歯科医師に相談しましょう。
口内炎は、予防や症状軽減のために、日常生活のなかでできることがたくさんあります。しっかりと治療を続けるためにも、口の中を健康に保ち、体力を維持できるよう、医師や看護師、栄養士などと相談しながら、ご自身の状態にあわせて、できることから始めてみましょう。