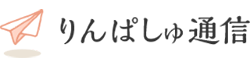第1回 リンパ腫は「3つのタイプ」ごとに歩んで行こう〜知っておきたい、診断がつくまでのながれ〜

医療法人財団順和会 赤坂山王メディカルセンター
(国際医療福祉大学医学部 血液内科学 教授)
畠 清彦(はたけ きよひこ)先生
リンパ腫は種類が多く、診断がつくまでに時間がかかるケースもあります。患者さんのなかには、⼀刻も早く治療を始めたいとあせりを感じてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、リンパ腫は大きく3つのタイプに分けられ、それぞれ診断がつき治療が始まるまでの時間や進め方が異なります。今回は治療に取り組む前に知っておきたい「診断がつくまでの流れ」について、畠先生にお話を伺いました。
 リンパ腫の「3つのタイプ」とは何でしょうか?
リンパ腫の「3つのタイプ」とは何でしょうか?
畠先生(以下、敬称略)病気の種類や進行具合から、どのようなスピード感で診断・治療を進めていく必要があるかを表したリンパ腫のタイプのことです。私は、リンパ腫が疑われる患者さんを、とにかく早い治療が必要な「超急性」、なるべく早い治療が必要だけれども治療の効果を⾼めるためにしっかりと病型(びょうけい)(リンパ腫の種類)の診断をつける必要がある「急性」、⽐較的ゆっくりあわてず診断をつけてから治療を⾏える「インドレント」の3つのタイプに分けて考えています※1。
※1 リンパ腫の進⾏のスピードは、医学⽤語では悪性度(あくせいど)という⾔葉で表されます。進行が速いものは悪性度が⾼い、進⾏が⽐較的ゆっくりしたものは悪性度が低いといいます。進⾏のスピードが速いということと、現時点でどこまで病気が進⾏しているかは別の話になります。ここでは総合的に判断した診断・治療の急ぎ具合によって、便宜的に3 つのタイプに分けて説明しています。

 それぞれどのくらいのスピードで診断がつくのですか?
それぞれどのくらいのスピードで診断がつくのですか?
畠 「超急性」のリンパ腫の場合は、診断を早くつける必要があります。そのため当院では、症状や⾎液検査、患者さんのお話から「超急性」が疑われる場合は、すぐに⼊院して確定診断のための⽣検(せいけん)を⾏います※2。場合によっては、来院された当⽇や翌⽇に⽣検を⾏うケースもあります。⽣検とは、病変部位の組織を針を⽤いたり⼿術によって採取して調べる検査で、リンパ腫の診断には⽋かせません。ただ、⽣検をしてから専⾨の病理医が診断をつけるまでには、どうしても週単位の時間がかかります。そのため「急性」の場合も、すぐに⼊院せずともなるべく早く⽣検をして診断をつけるようにします。患者さんにも、「超急性」や「急性」の場合は、万難を排してでも⽣検の⽇程を最優先していただくようお話ししています。早く診断をつけることが、その後の病気のより良い経過の第⼀歩になります。
「インドレント」の場合は病気の進⾏が⽐較的ゆっくりなので、患者さんの都合も相談しながら⽣検をする⽇にちを決め、時間をかけて診断をつけます。

※2 診断に要する時間や進め方は病院によっても異なるため、主治医とよく相談しましょう。
 ⽣検を早く⾏うためには、どうしたらいいですか?
⽣検を早く⾏うためには、どうしたらいいですか?
畠 ⽣検をするにあたっては事前に準備が必要なので、そのための検査などをします。⽣検をしたときに傷が外から⾒えにくく、かつ摘出しやすいリンパ腫がどこにあるかを調べたり、もし全⾝⿇酔が必要な場合は患者さんの健康状態が⿇酔に耐えられるかどうかを調べたりします。「超急性」や「急性」の場合は、⽣検の準備に必要な検査を、早くできるものから並行して進めていきます。

 診断をつけるための検査は、他にもするのですか?
診断をつけるための検査は、他にもするのですか?
日本血液学会 編:造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版,2023
「第Ⅱ章リンパ腫 Ⅱリンパ腫 悪性リンパ腫総論」
木崎昌弘 監:よくわかるがん治療 血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫, 主婦の友社, p34, 2020
 診断がついた後も、検査をするのですか?
診断がついた後も、検査をするのですか?
畠 患者さんにふさわしい適切な治療⽅法を決めるために、さまざまな検査や確認を⾏います。
治療によって他の病気が悪化しないか、逆に他の病気のためにお薬の副作⽤が出やすくならないかなどを⼊念に調べる必要があります。

 診断・治療までの流れは、患者さんごとに⼤きく異なるのですね。
診断・治療までの流れは、患者さんごとに⼤きく異なるのですね。
畠 そうですね。医師は患者さんの病気のタイプに合わせて診断の手順を調整し、一人ひとり異なる患者さんの背景も考えて治療⽅法を選択するので、同じタイプのリンパ腫でも患者さんごとに治療が異なる場合があります。そのため、医師をはじめとする医療者と患者さんの密接なコミュニケーションも、患者さん⾃⾝の治療を左右する重要なポイントです。私たち医療者はチームのなかで患者さんを⽀える体制を整えています。疑問に思うことがあれば、医師やメディカルスタッフに相談し、納得してともに適切な治療の道を歩んでいきましょう。


Dr.畠のアドバイス
医療法人財団順和会 赤坂山王メディカルセンター
(国際医療福祉大学医学部 血液内科学 教授)
畠 清彦先生
医師とのコミュニケーションのコツ
 段階をおって病気を理解しましょう
段階をおって病気を理解しましょう
リンパ腫は、種類や治療法もさまざまで、複雑な病気です。不安な気持ちでいっぱいなときは、医師の話がうまく理解できないこともあるかもしれません。でも、医師はそんな患者さんの気持ちの状態に合わせて説明してくれるはず。また、看護師や薬剤師も、患者さんの疑問に答えてくれます。あせらず、⼀つひとつ段階をおって理解していきましょう。
 質問は⼤事なものだけにしぼって、メモをしておきましょう
質問は⼤事なものだけにしぼって、メモをしておきましょう
⼈は⼀度に多くのことを覚えたり、理解するのは難しいといわれています。質問は、本当に⼤事なものを3〜4つにしぼって、あらかじめメモをしておきましょう。その他の質問は、次の機会や必要になった時に聞くことができます。 患者さんがきちんと納得して、前向きに治療に取り組んでいることが伝わってくると、医師としても嬉しいものです。リンパ腫の治療は時間がかかることもあるので、お互いに良好な患者-医師関係を築いていくことも⼤切だと考えています。