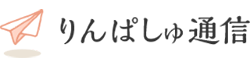FLの治療(移植など)
監修:
独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター 副院長
永井 宏和(ながい ひろかず)先生
造血幹細胞移植
FLでは初発の場合は、造血幹細胞移植が用いられることはほとんどありません。再発の進行期では選択肢のひとつになり、とくに抗がん剤治療で効果がみられた後、さらに徹底してがん細胞を減らすために移植を検討することがあります。身体への負担が大きい治療法なので、患者さんの全身状態などを考慮して、移植を行うかどうかを決めます。
造血幹細胞移植には、患者さん自身の幹細胞を用いる自家(じか)造血幹細胞移植と、ドナーから提供された幹細胞を用いる同種(どうしゅ)造血幹細胞移植があります。同種移植のほうが治療に伴うリスクは高いですが、再発が少なく治癒をもたらす可能性があると考えられており、いずれのタイプの移植も行われることがあります。ここでは、自家造血幹細胞移植について解説します。(同種造血幹細胞移植については、成人T細胞白血病リンパ腫の項を参照してください。)
 自家造血幹細胞移植の流れ
自家造血幹細胞移植の流れ

(イメージ図)
チーム医療のための血液がんの標準的化学療法(直江 知樹, 堀部 敬三 監),
メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2013 を参考に作成
自家造血幹細胞移植の治療期間は、前処置の方法や移植後の患者さんの状態などによって異なります。血液中から造血幹細胞を採取するのに採取準備を含めて1週間程度かかります。移植の1週間ほど前から前処置を開始し、移植後は生着まで約2週間、退院するまで約1ヵ月程度かかる場合が多いです。1)
 移植に伴う合併症
移植に伴う合併症
日本血液学会編:造血器腫瘍診療ガイドライン 第3.1版(2024年)Web版,2024
「第Ⅱ章リンパ腫 Ⅱリンパ腫 1 濾胞性リンパ腫」
飛内賢正 監:血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫, 講談社, p45, 2015
1)永井正 著:図解でわかる 白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫, 法研, p42-43, p172, 2016
治療後の経過観察
治療効果が得られた場合も、再発する可能性は否定できないため、定期的な経過観察が必要です。
 定期的な通院
定期的な通院
 注意すべき症状
注意すべき症状
経過観察中に以下のような症状に気づいたら、受診するようにしましょう。

リンパ節の腫れ(首、わきの下、足のつけ根など)

お腹や背中の圧迫感

原因不明の発熱、だるさがつづく

吐き気、食欲不振

原因不明の頭痛や意識がぼんやりする
神田善伸 監:ウルトラ図解 血液がん, 法研, p59-p61, 2020を参考