監修:
公益財団法人慈愛会 今村総合病院 名誉院長兼臨床研究センター長、HTLV-1研究センター長
宇都宮 與(うつのみや あたえ)先生
リンパ腫の治療方針は、リンパ腫の種類や悪性度、ステージによって異なります。また、患者さんの年齢やからだの状態、どのような持病を持っているかなど、それぞれの患者さんの状態にあわせて治療法を決定します。
薬物療法と放射線療法が中心
リンパ腫の治療は、薬物療法と放射線療法が中心です。このほか、造血幹細胞移植を行う場合もあります。基本的に手術は行いませんが、胃や大腸などのリンパ節以外の臓器にリンパ腫がある場合には手術を行う場合もあります。
日本血液学会編:造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版,2023
①薬物療法
リンパ腫では、複数の抗がん剤を組み合わせて投与する薬物療法(多剤併用化学療法)が治療の中心になります。抗がん剤にはたくさんの種類があり、いくつかの抗がん剤を組み合わせることで効果を高めたりします。
非ホジキンリンパ腫の患者さんでは、抗体薬単剤療法や抗体薬と抗がん剤を組み合わせた治療法が行われます。リンパ種の種類によっては、3種類の抗がん剤とステロイド薬を組み合わせて行う「CHOP(チョップ)療法」や、CHOP療法に抗体薬を追加した「R-CHOP療法」という治療法を行うことがあります。このほかにもたくさんの組み合わせがあり、リンパ腫の種類によって使い分けられています。CHOP療法、R-CHOP療法は2回目の接種から外来での治療が可能な場合があります。
ホジキンリンパ腫の患者さんでは、4種類の抗がん剤を組み合わせたABVD療法は外来での治療が可能な場合があります。
日本血液学会編:造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版,2023
国立がん研究センター中央病院:「CHOP(チョップ)療法」
(https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/pharmacy/010/pamph/DLBCL/010/index.html)
[ 2023年9月閲覧]
抗体薬登場
研究開発により増える治療の選択肢
抗体薬の登場により、リンパ腫の治療法は大きく変わりました。びまん性大細胞型B細胞リンパ腫や濾胞性リンパ腫などでは、現在では抗体薬を用いた治療も行われています。新しい薬の研究開発は国内外で続けられ、リンパ腫の患者さんに使用できる薬剤の選択肢は増えてきています。
伊豆津宏二:日内会誌, 2008; 97(7): 1620-1626
日本血液学会編:造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版,2023
②放射線療法
放射線療法は、リンパ腫のある部分を中心にからだの外から放射線(高エネルギーのX線)を当てて、がん細胞を破壊する治療法です。リンパ腫は放射線療法が効きやすいがんといわれています。
放射線療法は、リンパ腫の広がりが狭く、1カ所に集まっている場合に有効です。悪性度にかかわらず、病期の低いI期・Ⅱ期のリンパ腫で、単独もしくは薬物療法との併用で行われます。また、病気を治す目的以外にも、痛みを軽くして苦痛をやわらげるために行われることもあります。
正常な細胞へのダメージを最小限に抑えるため、放射線療法は少量ずつ照射します。そのため、放射線の照射時間は1回1~5分程度ですが、週に3~5回、何週かにわたって継続して行われます。一般的に外来治療が可能です。
飛内賢正 監:血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫, 講談社, p34-35, 2015
日本血液学会編:造血器腫瘍診療ガイドライン 2023年版,2023
国立がん研究センター がん対策情報センター:がん情報サービス「放射線治療の実際」
(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/radiotherapy/rt_02.html)
[2023年9月閲覧]
③造血幹細胞移植
血液のがんでは、血球のもととなる造血幹細胞(→リンパ腫とは)を移植する治療法があります。移植治療の前に大量の抗がん剤や全身への放射線療法を行い(前処置とよびます)、血球のもととなる正常な造血幹細胞を移植して治療する方法です。多くのリンパ腫では、再発した場合に移植を検討します。
造血幹細胞移植には、あらかじめ採取しておいた患者さん本人の造血幹細胞を移植する「自家移植」と、ドナー(提供者)の造血幹細胞を移植する「同種移植」という2種類の方法があります。
国立がん研究センター がん対策情報センター:がん情報サービス「造血幹細胞移植」
(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/index.html)
[2023年9月閲覧]
飛内賢正 監:血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫, 講談社, p44-45, 2015
| 自家移植 |
患者さん本人の造血幹細胞をあらかじめ採取、冷凍保存しておき、前処置後に点滴により患者さんのからだに戻す方法 |
| 同種移植 |
HLAと呼ばれる白血球の型が一致する血縁者や骨髄バンクや臍帯血の登録者(ドナー)の造血幹細胞を移植する方法
|
国立がん研究センター がん対策情報センター:がん情報サービス「造血幹細胞移植」
(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/index.html)
[2023年9月閲覧]、
飛内賢正 監:血液のがん 悪性リンパ腫・白血病・多発性骨髄腫, 講談社, p44-45, 2015 より作成
移植は患者さんのからだに大きな負担のかかる治療法のため、移植を受けられる患者さんには条件があり、年齢や病気の状態、また患者さんの意向にあわせて実施を検討します。最近では、前処置の強度を弱めて患者さんの負担を軽くした「ミニ移植」ができるようになり、高齢の患者さんでも移植が受けられるようになってきています。
国立がん研究センター がん対策情報センター:がん情報サービス「造血幹細胞移植」
(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/HSCT/index.html)
[2023年9月閲覧]
治療の副作用
薬物療法や放射線療法などの治療によって、副作用があらわれることがあります。あらわれる副作用は、抗がん剤の種類によっても異なりますし、患者さんごとに症状や強さはさまざまです。
薬物療法によくみられる副作用
- 嘔吐・吐き気
- 口内炎
- 便秘
- 味覚異常
- 手足のしびれ
- 脱毛
・・・など
放射線療法によくみられる副作用
- だるさ・吐き気・疲労感
- 腹部への照射による食欲低下・下痢
- 照射した部分の皮膚炎・粘膜炎
・・・など
放射線療法では、治療終了後半年以上経ってから起こる副作用もありますので、治療後もしばらくの間は注意が必要です。
国立がん研究センター がん対策情報センター:がん情報サービス「放射線治療の実際」
(https://ganjoho.jp/public/dia_tre/treatment/radiotherapy/rt_02.html)
[2023年9月閲覧]
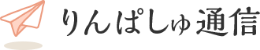
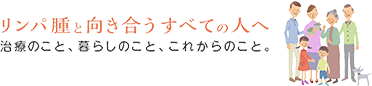
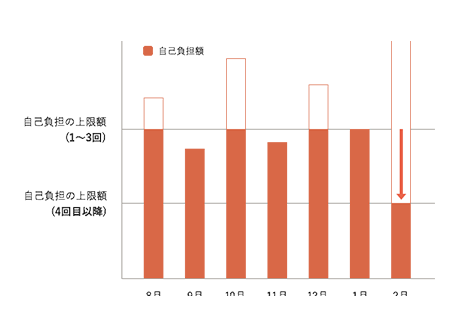
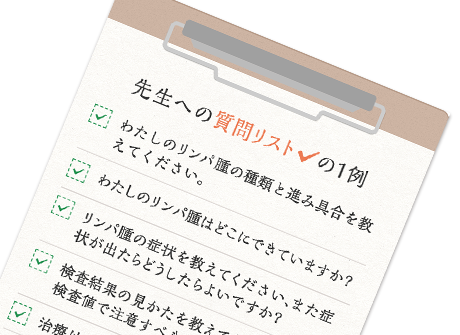



患者さんによって副作用には個人差があり、それぞれに応じた対処法があります。治療開始前に、主治医から副作用の症状や時期、対処法についての説明があります。緊急の対応が必要な副作用もありますので、どのような場合に病院に連絡すべきかなど、必ず確認するようにしましょう。つらい副作用の症状がある場合には、必ず主治医や薬剤師、看護師に相談するようにしてください。
公益財団法人慈愛会 今村総合病院
名誉院長兼
臨床研究センター長、
HTLV-1研究センター長
宇都宮 與先生